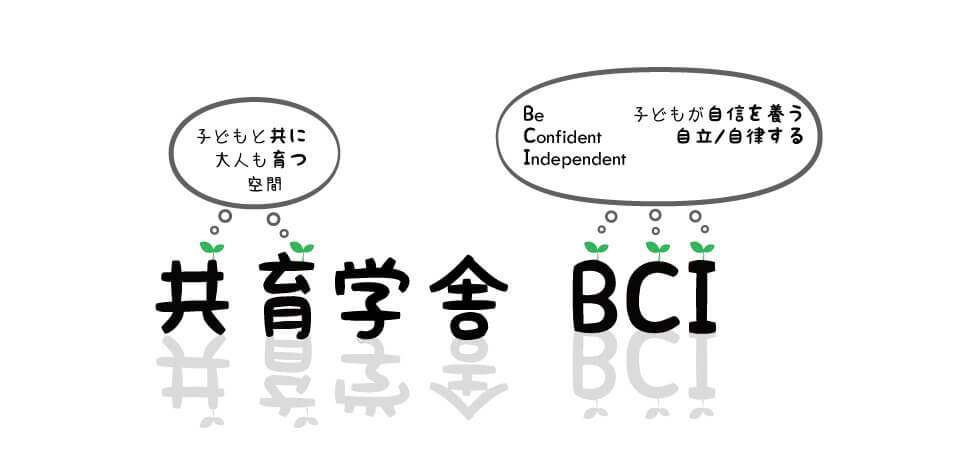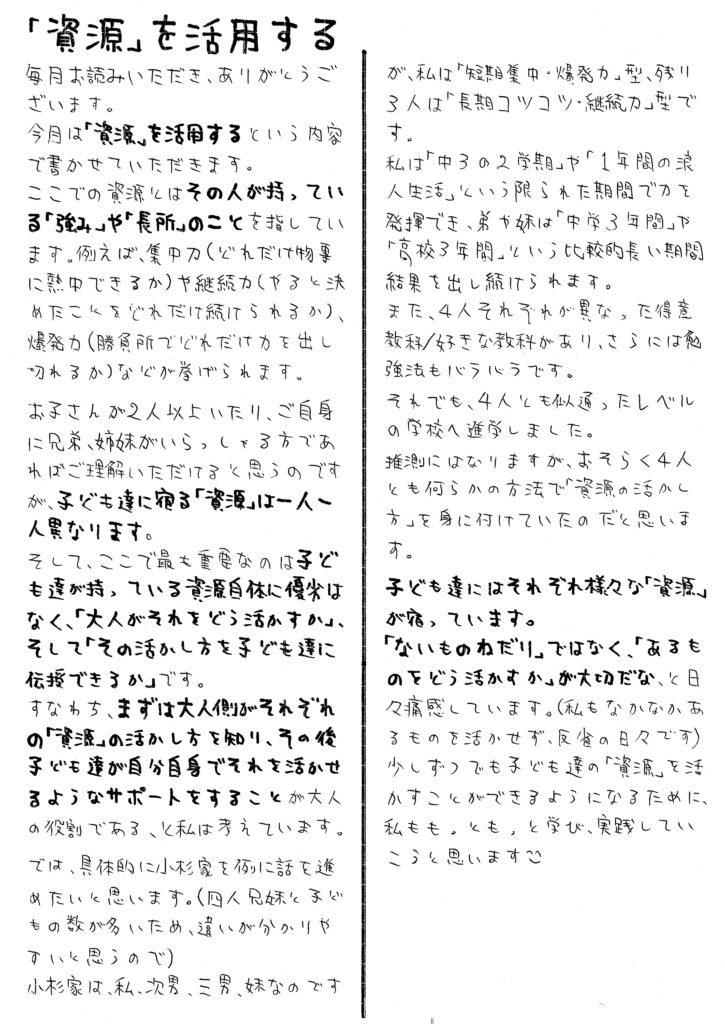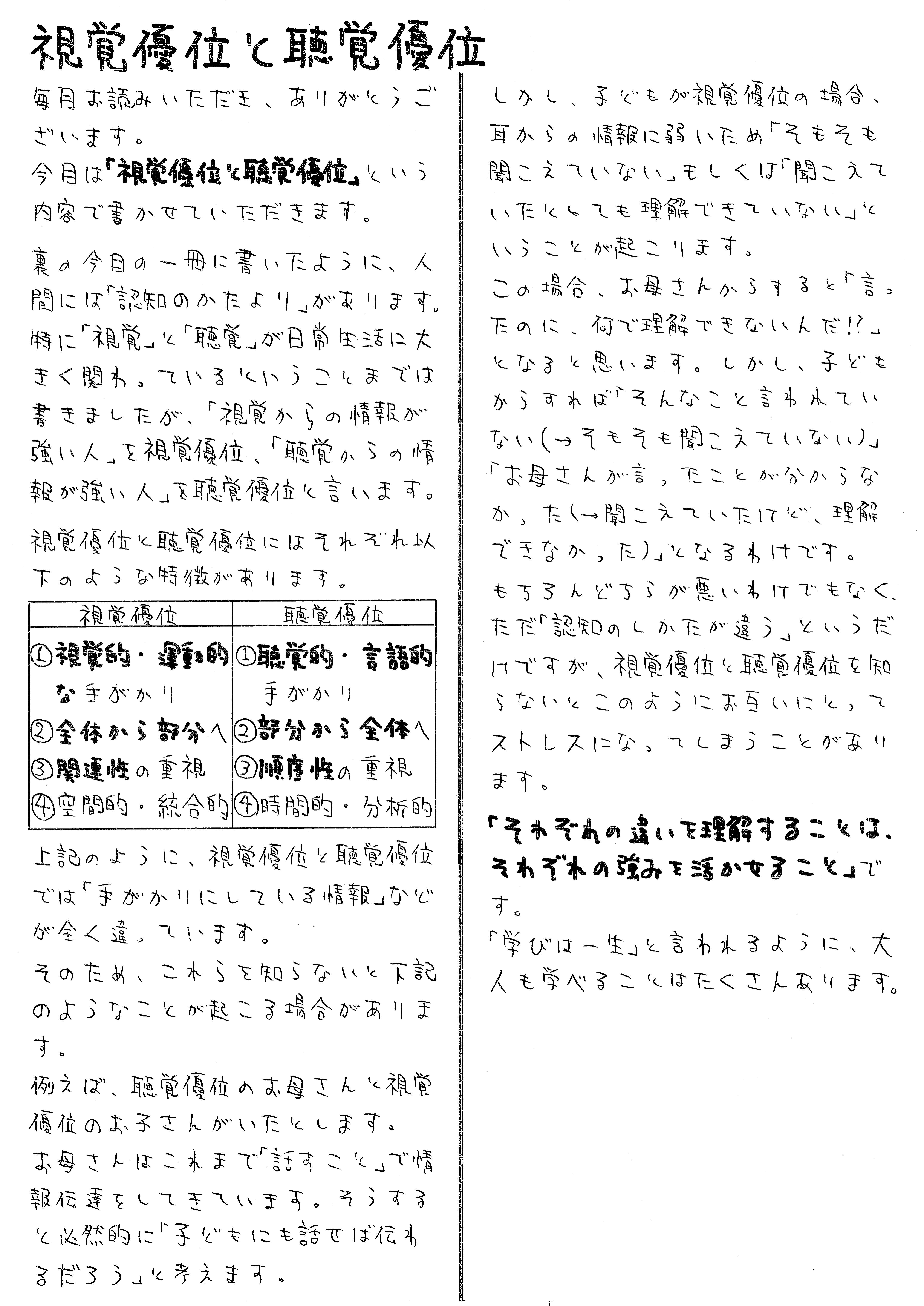こんにちは
 活字を読む習慣がなく「勉強が苦手」だけど学ぶのは好きな子のためのマナビノバ『共育学舎BCI』を主宰する、学びの土台ビルダーの小杉です
活字を読む習慣がなく「勉強が苦手」だけど学ぶのは好きな子のためのマナビノバ『共育学舎BCI』を主宰する、学びの土台ビルダーの小杉です
 この度はご訪問いただき、ありがとうございます
この度はご訪問いただき、ありがとうございます
7月に入り、夏本番といった陽気が続いていますね。連日猛暑日ですので、熱中症には気を付けてくださいね。
———————————————————————————————————————————
さて近年子ども達から「分からない」とだけ伝えられ、対応に苦慮することがあります。また新聞音読の際に記録用紙だけを黙って渡されることもあり、同様に「何をしたら良いのだろう」と戸惑うことがあります。これらに共通するのは、「言葉にせずとも、意図を汲み取ってほしい」と考えている点ではないかと思います。
家族間や親しい友人との間でのやりとりであれば、相手に忖度してもらっても構わないと思います。しかしそうした特殊な環境以外では、自分のやってほしいことは言葉にして伝える必要があると考えますし、そうしなければ伝わりません。そのため上記のような場面では、私は敢えて物分かりの悪い大人を演じることがあります。
前者に対しては「『分からない』という言葉だけでは、分からない状態にあることしか伝わらないよ。何を尋ねたいのかをもう少し具体的にしてごらん。」と伝え、後者に対しては「何をしたら良いのかな?」と尋ねます。そうすると子ども達ははっとした表情を見せながらも、自分の言葉で伝えようとしてくれます。その様子を見ると、今までそうした機会がなかっただけであって、きちんと伝えられることが分かります。
———————————————————————————————————————————
とかく大人は先回りして、子どもを助けがちです。それ自体は悪いことではないですが、子ども自らが行う機会を奪う行為でもあります。特に「分からない」とだけ伝えられて、説明なしにこちらが勝手に意図を汲み取ってしまうケースに関しては、非常に大きな問題があると感じます。
まずこちらが勝手に忖度してしまうと、子ども達は自分で説明する機会を失います。相手に説明しようとすれば、自ずと自分なりに論点を整理する必要がでてきます。実はこの過程で疑問が解決することもあるため、その機会の喪失は子どもにとって大きな損失です。
またこちらが忖度して意図を汲み取ると、子どもが実際に質問したいこととは全く違うことを読み取ってしまう可能性があります。余計に時間がかかるだけで、疑問が解決しないのは本意ではないはずです。
さらに自分の中で腹落ちさせるには、自分自身を納得させられるだけの説明を拵えなくてはなりません。その際、違った常識を持つ他者に対して説明した経験は活きてくるはずです。
———————————————————————————————————————————
子ども達からすると、「分からない」は全て同じように見えるかもしれませんが、一口に「分からない」と言っても分からなさのグラデーション(分からない度:0-100)によって、差異も当然あるはずです。それを一緒くたに「分からない」と纏めてしまうのは危険ですし、度合いによって分別する過程にこそ学びが詰まっていると思います。また分別すれば、それぞれに適した対応策を選べます。
質問するとは、相手に丸投げして自分の意図を読み取ってもらうことではなく、自分なりに論点を整理し、その上で分からないことをピンポイントで尋ねることだと思います。 「分からない」だけではなく、少なくとも「何が分かって、何が分からないのか」までは説明できるようになってほしいと思います。
———————————————————————————————————————————
世田谷区の桜丘2丁目で活字を読む習慣がなく「勉強が苦手」だけど学ぶのが好きな子の強みや長所を活かしながら、学びの土台を築くサポートをしています。(→学びの土台についてはこちらを参考にしてください)
その中でも特に「自分の好きなことを、楽しそうに話してくれる子」「(大人数よりも)少人数の時に輝く子」と共に学びたいです(不登校の子も大歓迎です)♫
また無学年・少人数制のマナビノバなので、今までの学習内容に抜けがあっても対応可能です
ご興味のある方は、ご連絡ください。無料体験も受け付けています →資料請求・無料体験申込はコチラ
→資料請求・無料体験申込はコチラ
私が塾で行っている「新聞音読&要約」を紹介する動画をアップいたしましたので、ご活用ください。